神社
阿保神社

阿保神社は菅原道真を祭神とします。境内には「史跡阿保親王住居址」の石碑が建てられています。…
詳細ページへ
田坐神社

延喜式内の神社で、三代実録によると、清和天皇の貞観4年(862)4月26日に無位より従五位下を授けら…
詳細ページへ
屯倉神社

屯倉神社は、天慶5年(942)に菅原道真を祭神として創祀されたと伝えられています。当地にはもともと、…
詳細ページへ
熱田神社

本殿は、一間社流造で、境内には合祀されている稲荷大明神社、龍神大神社、稲荷神社、金毘羅大権現社、庚申…
詳細ページへ
深居神社

立石と深居神社立石は、いまでは「歯神さん」としてまつられています。立石前には中世の一石五輪塔が2基お…
詳細ページへ
厳島神社

江戸時代には「弁財天宮」と称し、一津屋古墳の上に位置しています。戦国時代には一津屋城として利用された…
詳細ページへ
柴籬(しばがき)神社

仁賢天皇の勅命で創られたもので、丹比柴籬宮をこの地に造営し、また中国に使者を送った倭の五王の一人とい…
詳細ページへ
我堂八幡宮

我堂八幡宮は厄除宮として有名です。江戸時代の延宝8年(1680)の「我堂村検地絵図」では社名がなく、…
詳細ページへ
布忍神社

布忍神社は速須佐男之尊、八重事代主之尊、武甕槌雄之尊の三神を祀っています。社伝によると十八町北方の天…
詳細ページへ
正井殿

江戸時代には、神木「連理の松」が有名であったらしく、江戸時代中期・延宝7年(1679)に刊行された「…
詳細ページへ
丹南天満宮

丹南天満宮は丹南の産土神社で、菅原道真、天照大神、天児屋根命が祭神として祀られ、丹南藩主高木氏も代々…
詳細ページへ
産土(うぶすな)神社

室町時代には神仏習合思想のもとに神宮寺として再建され、明治時代の初期まで祭神を牛頭(こず)天王として…
詳細ページへ
黒田神社

「延喜式」にも記載された由緒ある神社で、中世より北條天神または天王と呼ばれ、「稲霊(いなだま)」を祀…
詳細ページへ
住吉神社

1813年に再建立された本殿は、江戸時代後期の特色をよく伝えています。
10月の第2月…
詳細ページへ
西代神社

毎年10月には、市の無形文化財である「西代神楽」が神社境内で奉納されます。
約250年…
詳細ページへ
長野神社

長野恵比須としてもよく知られている神社です。
室町時代後期建立と推定される一間社流造の…
詳細ページへ
烏帽子形八幡神社

国道371号線の西側、烏帽子形山の中腹にあり、入母屋造の本殿は重要文化財の指定を受けています。
詳細ページへ
高向神社

高向・日野地区の氏神。本殿は切妻平入で珍しく、市の文化財に指定されています。また10月上旬には、日野…
詳細ページへ
加賀田神社
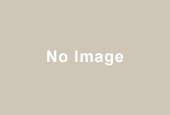
本殿は極彩色檜皮葺流造で市の文化財に指定されています。…
詳細ページへ
天神社

滝畑7カ村の氏神で、もとは大梵天王社と称していました。本殿は市の文化財に指定されています。…
詳細ページへ
千代田神社

神社には、立派な楠が何本かあり、
秋祭りには“だんじり”が宮入…
詳細ページへ
赤坂上之山神社

767年、行基により河内国錦部郡の総社として創建されたと伝わっています。
隣接する神宮…
詳細ページへ
八幡神社

八幡神社は、石清水八幡の神体を勧請(かんじょう)したといわれ、その創建はかなり古く、鎌倉時代にはすで…
詳細ページへ
川上神社

10月の秋祭りには、満1歳を迎えた子供が親に抱かれ、行司立合いのもと本殿前にてにらみあう「稚児相撲」…
詳細ページへ
蟹井神社

10月9日・10日に秋祭りがあり、9日の夜は天見の3地区から高提灯を仕立てて神社の下に集まり、祇園囃…
詳細ページへ
科長神社

科長神社は、平安時代の『延喜式』という書物に記録された、いわゆる式内社と呼ばれる由緒のある神社で、級…
詳細ページへ
狭山神社

延喜式内社の格の高い神社で、南北朝動乱で社殿が焼失し、室町期に再建されました。境内には狭山池の守護神…
詳細ページへ
三都神社

金剛寺から紀州熊野神社に至る街道に沿っているので、熊野神社とも呼ばれます。光明院・西室院・地蔵院など…
詳細ページへ
板茂神社

板茂神社は古くから板持字尾ノ上に鎮座する村社でしたが、明治40年南河内郡赤阪村建水分神社に合祀され、…
詳細ページへ
佐備神社

佐備神社は天安2年(858年)、文徳天皇の創建と伝えられ、江戸後期(1801年)に刊行された「河内名…
詳細ページへ
錦織神社

古代に錦部郷と呼ばれたこの地の守護神を祀ったとされ、唐(とう)破風(はふ)と千鳥(ちどり)破風(はふ…
詳細ページへ
美具久留御魂神社

大きな鳥居から延びる参道の奥には拝殿があり、崇神天皇が大国主命を祀ったのが始まりと伝えられています。…
詳細ページへ
飛鳥戸神社

竹内街道から飛鳥の集落に抜ける丘陵上にある神社です。古代の渡来系氏族「飛鳥部造」が建立したと伝えられ…
詳細ページへ
杜本神社

現在の祭神は、経津主命・経津主姫命とされていますが、平安初期には百済宿袮永継とその祖先の飛鳥戸氏を祀…
詳細ページへ
壷井八幡宮

河内源氏といわれる源頼信の子と孫にあたる頼義と義家が創建。江戸時代に再建されました。境内には義家の子…
詳細ページへ
大津神社

古代、水運にかかわっていた渡来系氏族、津氏一族の氏神。茅の輪をくぐって安全を祈願する、夏越しの祭りで…
詳細ページへ
白鳥神社

社伝では、軽里西方の伊岐谷(いきだに)に創建され「伊岐宮(いきのみや)」と呼ばれていました。 その後…
詳細ページへ
誉田八幡宮

欽明(きんめい)天皇の詔勅で応神陵の後円部に設けられた日本最古といわれる八幡宮。国宝の神輿(しんよ)…
詳細ページへ
建水分神社

後醍醐天皇の命により楠木正成が再建。春日造りの中殿、流れ造りの左右両殿など建築は非常に巧妙で、国の重…
詳細ページへ
磐船神社

神木の栂(とが)にちなみ、通称・栂の宮と呼ばれ、饒速日命(にぎはやひのみこと)を祭っています。磐楠船…
詳細ページへ
鴨習太神社

延喜式(えんぎしき:平安時代の書物)に河内国石川九社にものせられている古社で、1000年以上も前から…
詳細ページへ
壹須何神社

延喜式にも見える古社で、祭神は、はじめは蘇我氏の本支族がその祖廟として「宗我石川禰」をまつったといわ…
詳細ページへ
志貴県主神社(しきあがたぬしじんじゃ)

「延喜式」に記載のある式内社で、社名は、古代にこの地域に志紀県という地方行政単位があり、それを治めて…
詳細ページへ
伴林氏神社(ともはやしのうじのじんじゃ)

古代豪族の大伴氏やその一族である林氏の祖先神の道臣命(みちのおみのみこと)と天押日命(あまのおしひの…
詳細ページへ
辛國神社(からくにじんじゃ)

平安時代の延喜式神名帳にも記載のある式内社。当初は物部韓国氏の氏神として祭られたといわれています。参…
詳細ページへ
道明寺天満宮

土師氏(はじし)の氏神として創建されました。土師氏の子孫である菅原道真の死後、道真を主神とした天満宮…
詳細ページへ

